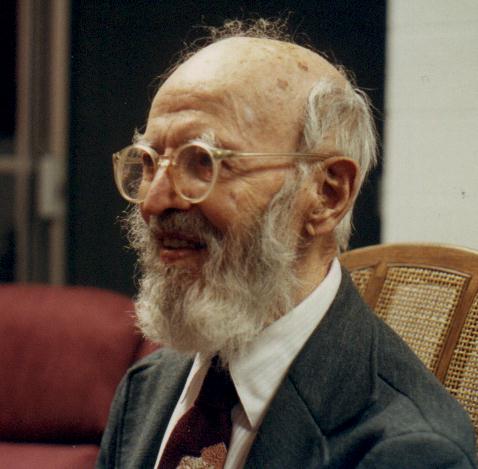統一原理の神観について(9)
三番目に、神と被造世界の関係に関して、統一原理と伝統的なキリスト教神学を比較してみたいと思います。
この問題について私の著書『神学論争と統一原理の世界』では、34ページから始まる第1章2において「神は悲しんだり後悔したりするか?」 というタイトルで論じておりますので、ちょっとその部分を読んでみたいと思います。
「神は悲しんだり後悔したりするか? 答は聖書をみれば一目瞭然。創世記第6章6節には『主は地の上に人を造ったのを悔いて、心を痛め』と書いてあるし、その後の旧約聖書全体に、神が不信の民イスラエルに幾度となく裏切られ、失望と落胆を繰り返しながら嘆き悲しみ、時には怒り、罰を与えながらも最終的には許し、愛して導いてきた歴史が連綿とつづられているではないか。神が悲しんだり後悔したりしているのは周知の事実で、それができるかどうかというのは愚問ではないのか? と言いたいところだが、そう単純にいかないのが神学の難しさである。
なぜなら、伝統的なキリスト教神学には、これとは全く相反する神観があるからだ。普通、神とはどんな存在かと聞かれて思い浮かべるのは、唯一絶対、全知全能、完全無欠、第一原因者、といったところだろうか。もしこれが本当なら、神は最初からすべてを知っていて完成し、すべてをコントロールしているはずだから、人間の行動に左右されて後悔したり、嘆き悲しんだりするのは不可能だということになる。」(『神学論争と統一原理の世界』p.34)
この、神が悲しむかどうかという問題なんですが、私たち統一教会の食口は神が悲しんでいるというのは当然のことのように思っておりますし、聖書の中にもそう思わせる聖句というのは、実はたくさん出てくるんです。神様の嘆きというような内容です。ところが、哲学的な神学になりますと、神は唯一絶対、全知全能、完全無欠なんだから、どうして悲しまないといけないんだということになるわけです。これが神学の難しいところであるわけです。要するに、「哲学的な神」と「聖書の神」との間の大きな矛盾がキリスト教神学にはあるということです。
「伝統的な神学において描写されている『哲学的な神』は、人間と親密に交わる人格的な『聖書の神』とは、かなりイメージの異なる『絶対的な超越者』だ。それは何かを動かすことはあっても動かされることはなく、他に何かを与えることはあっても与えられることはない。完全無欠でそれ自体で完結しているから、進歩・発展することもない。したがって人間を上から一方的に愛することはあっても、人間の行動によって喜んだり、逆に悲しむこともないという無関心な神である。ましてや、人間の行動に左右されたり影響を受けたりするなんてあり得ないのである。」(『神学論争と統一原理の世界』p.35)
このように、伝統的な神学における神というのは「哲学の神」に近いものであって、およそ人間味というものを感じないような神様の姿であったということです。
「このように『哲学的な神』と『聖書の神』との間には大きな隔たりがあるが、どうしてこのようなことになってしまったのか? それは伝統的なキリスト教神学が、ギリシア哲学と聖書の思想のブレンドであったことに原因がある。新・旧約聖書は物語や教訓の寄せ集めであり、そこには哲学的体系がなかった。最初のうちはそれで十分だったが、キリスト教がヘレニズム世界へ広がっていくにつれて、教義を体系的に整えて知的に説明し、さらには正統と異端とを明確に定義する必要が出てきた。その当時、最も進んだ哲学者と言えばプラトンとアリストテレスであったから、神学を組み立てる論理的な骨格として、ギリシア哲学を借用したわけである。」(『神学論争と統一原理の世界』p.35)
さきほど地図を見せて説明しましたけれども、旧約聖書や新約聖書は物語や教訓の寄せ集めであって、およそ哲学というようなものはなかったんですね。それがヘレニズム世界に広がっていくにしたがって、教義を体系的にするために哲学が必要になってきて、そのときにはプラトンやアリストテレスの哲学が当時最高のものであったために、これを借用したということです。ですから、キリスト教神学というのは、プラトンとアリストテレスの哲学を骨組みにして、そこに聖書を肉付けして出来上がった、いわば「聖書とギリシア哲学の思想のブレンド」であったということになります。
「これによってキリスト教神学は学問的に洗練されたわけだが、ギリシア哲学と聖書の思想、この二つの思想の神観はどう考えてもミス・マッチだった。キリシアの哲学者たちが頭の中で思索して生み出した神は、まさしく前の段落で述べたような、宇宙の頂点に君臨する観念的な絶対者だった。そして神と人間の関係は、非人格的で一方通行だ。それに対して聖書の神は、ユダヤ民族とクリスチャンたちが苦難の中で信仰を通して出会った、いわば血の通った生きた神の姿であり、神と人間は深く人格的にかかわり合っている。
宗教的には、聖書の神の方が魅力的なのは言うまでもない。しかし哲学者たちは、それを単なる感情表現として片づけてしまい、学問的には洗練されていない価値の低いものとして片隅に追いやってしまった。その結果として、冷たく無関心な神のイメージができ上がってしまったのである。」(『神学論争と統一原理の世界』p.35-36)
というわけで、この二つの神観には大きなギャップがあるわけですね。「哲学の神」というのは宇宙の頂点に君臨する観念的な絶対者であり、神と人間の関係は、非人格的で一方通行です。一方、聖書の神は信仰者が人格的に出会った生きた神の姿です。そして、どちらが主流になったかというと、結果的にこの「哲学の神」の方が神学の主流になってしまい、「聖書の神」は単なる感情表現ということで、非本質的なものとして片隅に追いやられてしまったということです。
しかし現代になってくると、キリスト教神学の生成過程というものが研究されるなかで、これはちょっとおかしいんではないかと感じ、ギリシア哲学がキリスト教の神観に影響を与えた結果、聖書の中で表現されている神が本質的に失われてしまって、キリスト教の神観を歪めてしまった、これは一つの弊害だった、ということを現代神学の中で認めるようになってきたわけです。その代表的な神学者の中にアルフレッド・ノース・ホワイトヘッド(1861-1947)という人や、チャールズ・ハーツホーン(1897-2000)という人がいて、彼らが「プロセス神学」という神学を打ち立てて行きます。
このプロセス神学というのは、神様を静的で止まった形でとらえるのではなくて、常に動いている、ダイナミックな存在とする神学です。ですから、すべては「プロセス」であるという考え方です。そのような新しい現代的な哲学に基づいて、ギリシア哲学ではない新しいとらえ方で神学を打ち立てようという現代神学の一つの流れが「プロセス神学」であるということになります。これによって、聖書で表現されている神の姿というものをより哲学的に表現できるのではないかということで、プロセス神学が登場してきます。
私が統一神学校にいたときに組織神学を教えていただいた神明忠明先生という方がいらっしゃいます。この方は、統一神学校の第一期生で、日本人食口としては初めて神学博士号をとった人です。神明先生は、現代神学の中でもこのプロセス神学と統一原理と比較する論文を書いています。プロセス神学などは、古典的な神学に比べれば、神様と被造世界がダイナミックな関係を結ぶという点においては、一歩原理に近づいた神学ということもできるわけです。このように現代神学の中には、既存の神学の問題を乗り越えて、統一原理に一歩近づくような神学も存在するわけです。