伝統宗教における万物献祭③
このシリーズでは、宗教における供え物、献金、布施、喜捨などを一括して「万物献祭」と呼び、こうした行為が伝統宗教において広く行われており、信仰者の義務あるいは美徳として高く評価されてきたことを明らかにしています。
ここで『世界経典』から、犠牲、喜捨、供物、布施に関する聖句を挙げてみましょう。
まことにわれは、なんじに潤沢を授けた。それで、なんじの主を礼拝し、犠牲をささげよ。(イスラム教、コーラン 108.1-2)
なんじらは愛するものを喜捨せぬかぎり、正義を全うし得ないであろう。なんじらが喜捨するどんな物でも、神は必ずそれを知りたもう。(イスラム教、コーラン 3.92)
すべての供物は天に至る舟である。(ヒンドゥー教、シャタパタ・ブラーフマナ 4.2.5.10)
布施する者は実に神々のもとに赴く。 (ヒンドゥー教、リグ・ヴェーダ 1.125.5)
物惜しみする人は天の神々の世界にはおもむかない。愚かな人々は分かちあうことをたたえない。しかし心ある人は分かちあうことを喜んで、そのゆえに来世には幸せとなる。(仏教 スッタニパータ 177)
与えられるべきだと考えて、見返りが期待できぬ相手に、場所と時間と受者が適切な場合に与えられる布施は、純質的な布施と伝えられる。一方、見返りを望んで、または果報を意図して、渋々与えられる布施は、激質的な布施と伝えられる。(ヒンドゥー教 バガヴァッド・ギーター 17.20-22)
4.キリスト教における献金
『クリスチャン生活事典』(教会新報社:1981年)によると、キリスト教における献金の意義は、「神にささげ物をすることは祝福の基である」という聖書の教えに基づいています。献金とは神の恵みへの応答であり、イエス・キリストによって受けた神の恵みに対して、神への感謝としてささげる金銭である、と定義されています。その起源は旧約聖書における「ささげ物」であり、これは律法によって定められていました。
「地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主の聖なる物である」(レビ記27.30 )とあるように、産物の初の収穫と、収入の10分の1を感謝のしるしとして捧げていました。旧約時代のレビ人は、神殿に仕える特別の民で、彼らは一般の民のささげる10分の1のささげ物で生活するよう律法で規定されていました。
新約聖書におけるささげ物は、「恵みのわざ」と表現されました。コリント人への第二の手紙を書いた使徒パウロは、8章と9章で「神の恵みのわざ」である献金について、その本質、精神、心得について、次のように詳しく述べています。
兄弟たちよ。わたしたちはここで、マケドニヤの諸教会に与えられた神の恵みを、あなたがたに知らせよう。すなわち、彼らは、患難のために激しい試錬をうけたが、その満ちあふれる喜びは、極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て惜しみなく施す富となったのである。わたしはあかしするが、彼らは力に応じて、否、力以上に施しをした。すなわち、自ら進んで、聖徒たちへの奉仕に加わる恵みにあずかりたいと、わたしたちに熱心に願い出て、わたしたちの希望どおりにしたばかりか、自分自身をまず、神のみこころにしたがって、主にささげ、また、わたしたちにもささげたのである。(Ⅱコリ8.1-5)
さて、あなたがたがあらゆる事がらについて富んでいるように、すなわち、信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる熱情にも、また、あなたがたに対するわたしたちの愛にも富んでいるように、この恵みのわざにも富んでほしい(注①)。こう言っても、わたしは命令するのではない。ただ、他の人たちの熱情によって、あなたがたの愛の純真さをためそうとする(注②)のである。(Ⅱコリ8.7-8)
ここで注①は、「恵みのわざである献金を惜しまないでください」という意味で語っており、注②は、「献金は愛が真実であるかどうかが確かめられるものである」という意味で語っています。
パウロが献金の態度について語った代表的な聖句には以下のようなものがあります:
わたしの考えはこうである。少ししかまかない者は、少ししか刈り取らず、豊かにまく者は、豊かに刈り取ることになる。(Ⅱコリ9.6)
各自は惜しむ心からでなく、また、しいられてでもなく、自ら心で決めたとおりにすべきである。神は喜んで施す人を愛して下さるのである。(Ⅱコリ9.7)
パウロが献金の資源について語った代表的な聖句には以下のようなものがあります:
神はあなたがたにあらゆる恵みを豊かに与え、あなたがたを常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良いわざに富ませる力のあるかたなのである。(Ⅱコリ9.8)
パウロが献金の結果について語った代表的な聖句にはコリント人への第二の手紙9.10~14があり、以下のような内容を述べています:
①あなたがたの義の実を増して下さる
②すべてのことに豊かになる
③惜しみなく施すようになる
④神に感謝するに至る
⑤献金を受けた人々があなたがたを慕う
⑥献金を受けた人々があなたがたのために祈る
このように、「供犠」「喜捨」「布施」「献金」などの概念は、伝統宗教において神から受けた恵みに対する返礼であり、神に近づく道であり、神の祝福を受ける条件であると意義付けられており、感謝して惜しみなく捧げることが信者としての務めであると説かれていることが分かります。
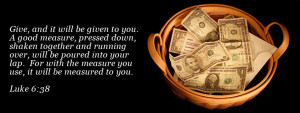
献金に関する新約聖書の言葉:「与えよ。そうすれば、自分にも与えられるであろう。人々はおし入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量をよくして、あなたがたのふところに入れてくれるであろう。あなたがたの量るその量りで、自分にも量りかえされるであろうから」

