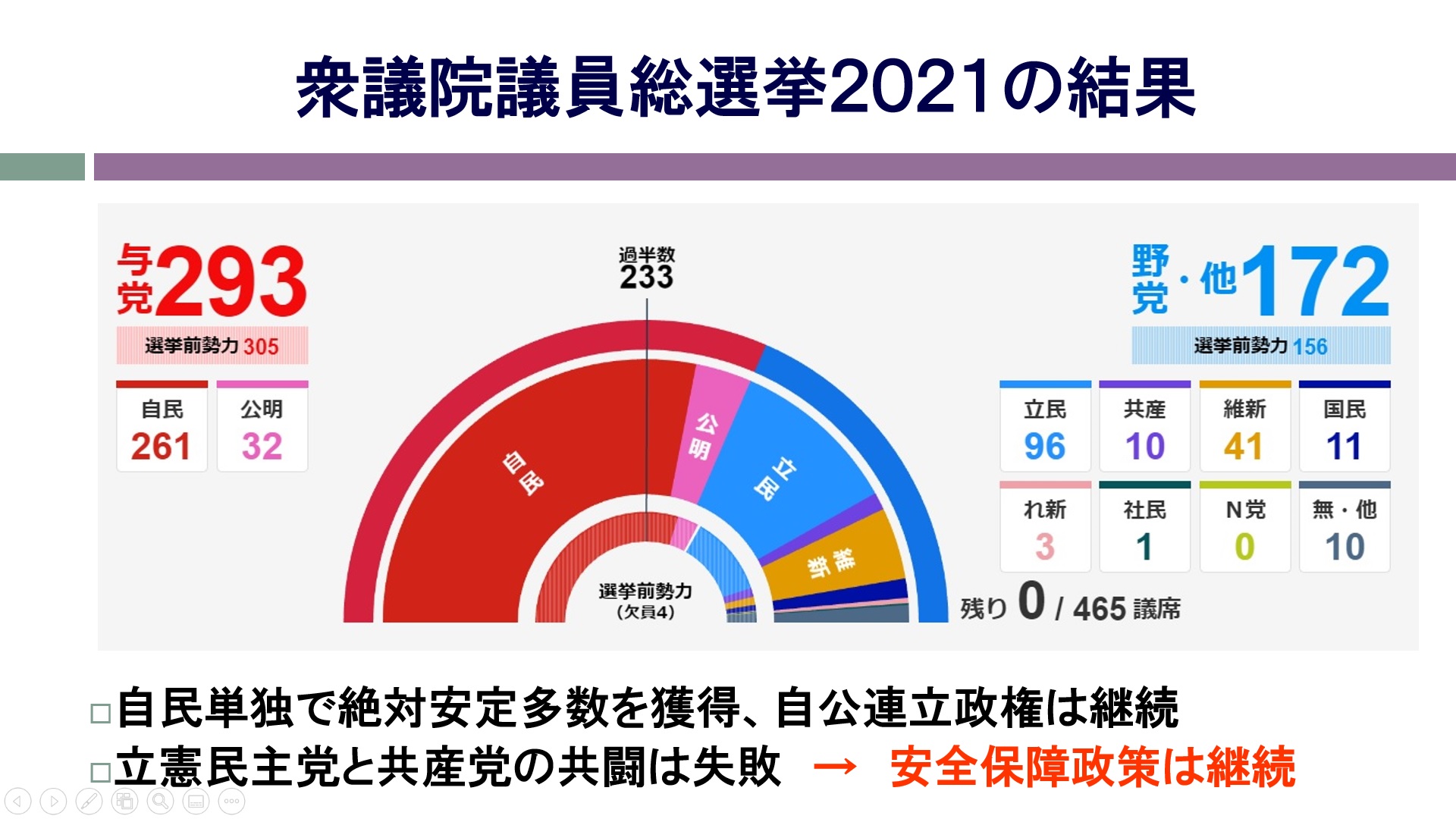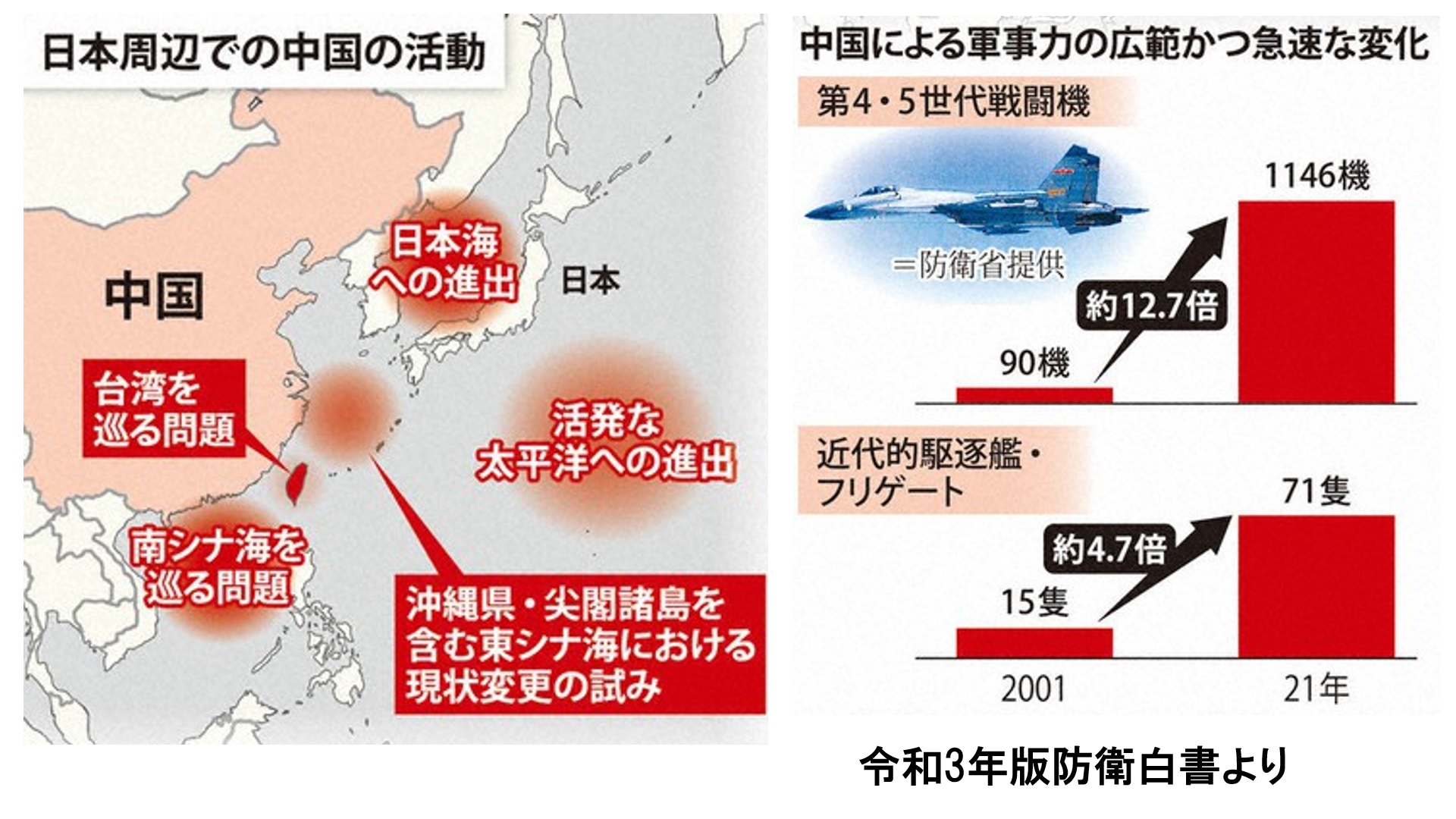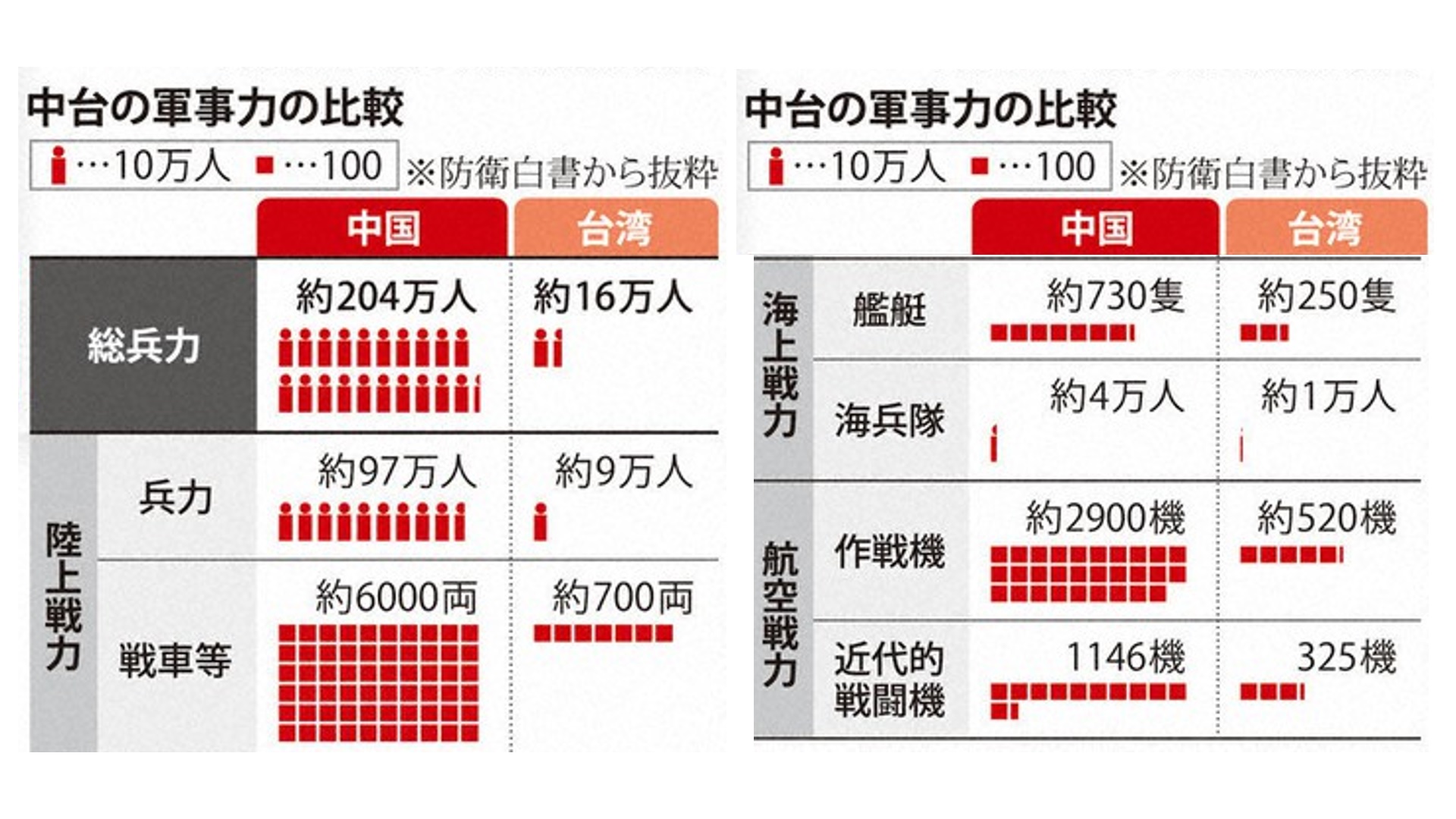第九章 第一回御出京の続き
天照皇大神宮教の経典である『生書』を読み進めながら、それに対する所感を綴るシリーズの第41回目である。第37回から「第九章 第一回御出京」の内容に入った。第九章では、大神様がいよいよ東京に出て行って教えを宣べ伝える様子が描かれている。大神様の東京における活動拠点は杉並区にある慈雲堂病院であったが、4月2日から約10日間、千葉県の四街道の開拓団に移動し、そこで御説法されることとなった。この開拓団は、旧陸軍練兵場に開設されたもので、復員軍人によって構成されていた。今回はそのときの出来事を扱うことにする。
開拓団では昼は婦人や子供たちが大神様の御説法を聞きに来たが、夜は男性たちがやってきた。彼らはみな元軍人であり、昔は威光を放っていたが、「ひとたび無条件降伏となってみれば、自らの生きる道を、彼らの腕で働き、額に汗して求めなくてはならなくなり、ここに集まっている人たちは、練兵場の跡を開墾して、一介の農夫として立ち上がろうとしていた人々」(p.285)であった。それだけに彼の心は荒んでおり、組織としての秩序もなく、不平不満が絶えない状態だった。こうした人々に対しても大神様はなんの遠慮会釈もなく説法された。その内容はこれまで大東亜戦争や天皇陛下について大神様が語ってきたことと基本的には同じ内容であるが、改めてポイントを抑えておこう。
①大東亜戦争は聖戦などではなく、他国に出て行って人殺しと泥棒をしただけだった。
②よその国を取る必要などない。日本の本土だけで十分だ。隣国は隣国であるのが良い。
③これからは正しい神と悪魔の戦いが始まる。それは祈りの戦いである。
④天皇は現人神ではなかった。置物の人形に過ぎなかった。だから人間宣言をした。
⑤いまや天皇に代わって天照皇大神宮教が天降ったので、神の国をつくるのだ。
⑥神州不滅とは日本が亡びないという意味ではなく、「神衆不滅」と書くのが正しい。神の子だけが不滅という意味である。だから神の子にならなければならない。
⑦八紘一宇の「紘」の字は、「光」と書かなければならない。他国を侵略しておいて八紘一宇を唱えても誰も受け入れない。
⑧このたびの日本の敗戦は神の計画であった。裸一貫になって再出発するためだ。
⑨真の神の召集令状は、真人間に立ち帰ることを求めている。
こうしてポイントを並べてみると、大神様はこれまで日本人が信じて来た国体イデオロギーを否定し、一つひとつの言葉に新しい解釈を施すことによって日本の再建を訴えていることが分かる。その意味で天照皇大神宮教はまさに戦後的な新宗教であり、既存の価値観が崩壊した危機の時代を革新的な解釈によって乗り越えようとした宗教であると言えるだろう。しかし、殉忠報国の思想で凝り固まった元軍人たちには、天皇に対する批評はにわかに受け入れがたく、半信半疑で聞いているものが多かったという。
ここで一人の者が以下のような質問をした。
「衣食住に魂とられるな、と言われるが、我々さしあたって明日の日に困っておる者に、まずパンを与えてくださるのが神ではないのですか。昔から衣食足って礼節を知るという諺もあるとおり……」(p.290-291)
しかし大神様はこれを言下に否定された。
「違う違う、まず真人間になれ。真人間になりさえしたら、お前らの生きる道は、天父が与えちゃる。自ら餓鬼道の世界に落ちちょいて、神に『まずパンを与えよ。』と言うたってそりゃだめじゃ。人間の道まっすぐ行けば、すぐに神や仏の世界、神や仏の世界に行きさえすれば、天にゃ無限の供給あり。人間にやりたいものは天にゃつかえておるけれど、人間のばかが裏道横道逃げ歩いて、天の供給をよう取らんのじゃ。天の供給の取れるところまで、まず自分で魂磨いて上がって来い。わしの肚には『一にも国、二にも国、三にも国』と言うものがおるのじゃ。」(p.291)
天照皇大神宮教は聖書やキリスト教を背景にした宗教ではないのだが、ここにはイエス・キリストの教えとの驚くべき類似性を発見せざるを得ない。それは考え方の内容においてだけでなく、「パン」というキーワードからも何らかの思想的ヒントを得たのではないかと思わざるをえないのである。日本人の主食はパンではなく米である。「明日の米を与えてください」という方が当時の日本人の生活からははるかに自然であるにもかかわらず、なぜあえて「パン」という表現を用いたのであろうか。たまたま軍人がパンと言ったというよりは、この部分は新約聖書に思想的ヒントを得たのではないかと私は考える。
人はパンで生きるのか、それとも神のみ言葉によって生きるのかというテーマは、新約聖書のマタイ伝4章に登場する。
「さて、イエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。そして、四十日四十夜、断食をし、そののち空腹になられた。すると試みる者がきて言った、『もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい』。イエスは答えて言われた、『「人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものである」と書いてある』」。(マタイ4:1-4)
新約聖書のこの部分に対する一般のキリスト教の解釈は、人が生きていく上で必要な栄養素は水や食料、空気などの外的・物質的な栄養素だけでなく、神の言葉という内的、精神的栄養素もあるのであり、この二つのどちらに最高の価値があるかと言えば、むしろ後者であるというものだ。そして「パンを石に変えろ」という悪魔の試練がもつ意味は、石はキリスト(神の子の立場)を指し、パンは人が現世で生きるのに必要な物質的なもの(食料・富)を指すのであるから、肉体的な欲望のために神の子としての自分の立場を捨てよと悪魔は誘惑していることになる。これにイエスは打ち勝ったということだ。
『原理講論』におけるこの聖句の解釈も基本的には同じ考え方に基づいている。
「この試練に対するイエスの答えは、『人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものである』(マタイ四・4)というみ言であった。元来、人間は、二種類の栄養素によって生きるように創造された。すなわち、自然界より摂取する栄養素によって肉身を生かし、神の口から出るみ言によって霊人体を生かすようになっているのである。」
「その石は結局、サタンの試練を受けているイエス自身を象徴するものであった。……それゆえに、サタンの最初の試練に応じたイエスの答えは、要するに、私が今いくらひどい飢えの中におかれているとしても、肉身を生かすパンが問題ではなく、イエス自身がサタンから試練を受けている立場を勝利して、すべての人類の霊人体を生かすことができる、神のみ言の糧とならなければならないという意味であった。」(以上、『原理講論』後編第二章モーセとイエスを中心とする復帰摂理、第三節イエスを中心とする復帰摂理より)
大神様の『一にも国、二にも国、三にも国』という言葉は、「まず神の国と神の義とを求めなさい」というイエス・キリストの教えに酷似している。「天の供給」という大神様の教えも、イエスの有名な「山上の垂訓」の思想と類似している。以下にその一部を引用するが、物質的な欲求よりも神の国を優先せよというイエスの教えと大神様の教えには明確な類似性がみられ、私にはこれらが無関係であるとは考えられない。
「それだから、あなたがたに言っておく。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで思いわずらい、何を着ようかと自分のからだのことで思いわずらうな。命は食物にまさり、からだは着物にまさるではないか。空の鳥を見るがよい。まくことも、刈ることもせず、倉に取りいれることもしない。それだのに、あなたがたの天の父は彼らを養っていて下さる。あなたがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者ではないか。あなたがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでも延ばすことができようか。また、なぜ、着物のことで思いわずらうのか。野の花がどうして育っているか、考えて見るがよい。働きもせず、紡ぎもしない。しかし、あなたがたに言うが、栄華をきわめた時のソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。きょうは生えていて、あすは炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装って下さるのなら、あなたがたに、それ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思いわずらうな。これらのものはみな、異邦人が切に求めているものである。あなたがたの天の父は、これらのものが、ことごとくあなたがたに必要であることをご存じである。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろう。だから、あすのことを思いわずらうな。あすのことは、あす自身が思いわずらうであろう。」(マタイ6:25-33)