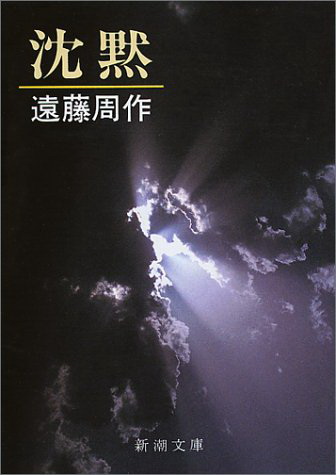土着化に失敗したキリスト教
キリスト教の「グレート・センチュリー」と呼ばれた19世紀以降、世界史はまさしくキリスト教文化圏の国々によって主導されてきた。19世紀から20世紀にかけて、近代化とはキリスト教文化圏である西洋の文化・制度を吸収することを意味したのであるし、キリスト教は信徒の数およびその生活水準において、群を抜いて世界一の宗教となった。
2008年のデータでも、世界人口67.5億人に対して、キリスト教徒の人口は22.5億人であり、二位のイスラム教人口15億人を大きく引き離している。世界人口に占めるキリスト教徒の割合は、現時点でも約33%を占める。(注1)
しかし日本という国は、多大なる宣教の努力にも関わらず、いまだにキリスト教とは疎遠な関係にある。日本は東アジアの中では最も近代化され西洋化された国でありながら、いまだにキリスト教徒の数は人口の1%にも満たない。キリスト教は日本においては依然として少数派であり、「バタ臭い」という一般的な言い回しにも表現されているように、「外国の宗教」とみなされているのである。(注2)
たとえキリスト教人口が少数でも、これから伸びていく兆しがあればまだ希望はある。しかし、日本においてこれからキリスト教人口が増加するであろうという予想する者はほとんどいない。日本におけるキリスト教の宣教は、「失敗」とまでは言わなくても「停滞」もしくは「行き詰まり」と表現するのがふさわしい状況にある。これは端的に言えば、キリスト教が日本の文化になじむことに失敗したことを意味している。
二つの異なる文化が出会おうとする時、そこには葛藤が生ずるものである。したがってキリスト教という西洋の宗教が日本に伝えられる過程においても、さまざまな文化的相克を生みだし、それが宣教の大きな障害となった。これは過去数世紀にわたる多大なる宣教の努力が、ほとんど実っていないという事実からも伺い知ることができる。異文化圏から伝わってきた宗教が、その地の文化的土壌になじんで、その国独自の宗教形態を発展させていく過程を「土着化」という。すなわち、キリスト教が日本に土着化するということは、キリスト教がその宗教的本質を保ったまま、日本人が文化的異質性や抵抗を感じないような、「日本的な」宗教となることを意味するのである。したがってキリスト教が「バタ臭い」ということは、それがいまだに土着化に成功していないということを意味する。
「土着化」のプロセスで必然的に起こるのが「シンクレティズム」である。キリスト教の根本主義においては、シンクレティズムは極めて否定的な意味合いでとらえられており、宗教的伝統の変質や歪曲とほぼ同じ意味で用いられている。その理解の根底には、カナン七族の信仰と混ざることによってヤハウェに対する信仰を歪めた古代イスラエル民族のイメージがある。しかし、現実的にはシンクレティズムはある程度必然的に起こるものである。現在西洋の宗教と考えられているキリスト教といえども、もともとはユダヤ的だったものがローマの文化に土着化し、それがさらにゲルマン民族の文化に土着化して出来上がったものだ。その間にキリスト教の内容は大きく変化した。それが東洋に伝えられれば東洋的になることは自然の理であり、西洋人はそれを非難できる立場にはない。
しかし実際問題として、キリスト教を日本に土着化させるということは、容易ならぬ仕事であった。この仕事を最初に手掛けたフランシスコ・ザビエルらのイエズス会宣教師たちは、戦略的には状況適応型のアプローチをとった。すなわち日本文化との相克をできる限り避けるように配慮しながらキリスト教を広めようとしたのである。
フランシスコ・ザビエルが1549年にゴアから日本へ航海した時、日本はフィリピンのように宣教の大勝利の地になるかに思われた。楽観的な宣教師は、1577年に「もし十分な数の宣教師さえいれば、日本全体が10年間でキリスト教化されるであろう」と書いている。イエズス会の宣教師は、1579年にはキリスト教に改宗した者たちの本拠地としての新しい街である長崎を建てることに成功し、既に10万人の日本人改宗者がいると主張した。1587年には彼らは20万人の改宗者と240の教会を有していると主張した。
しかしながらキリスト教信仰の急速な拡大は突如として座礁した。フランシスコ会とプロテスタントの宣教師が到来して論争を始め、宣教師たちは政治に巻き込まれた。日本の統治者は、宣教師たちをスペインの侵略者たちの先鋒であるとみなすようになった。1614年には、将軍家康は宣教師たちを日本から追放する為の勅令を出し、その時から過酷な迫害が始まった。1614年から1646年までの間に、4045名の殉教者が出た。1638年の鎖国令によって、日本は外国人に対して閉ざされた。そして1614年の時点ではおよそ30万人いた日本のキリスト教徒は、結局1697年までに少なくとも表面上は絶滅してしまったのである。(注3)
日本における宣教活動の多大なる困難は、遠藤周作の小説「沈黙」の中に想像力豊かに表現されている。以下は、日本に不法侵入したイエズス会の司祭ロドリゴと日本の役人との会話である。想定されている年代は1650年頃だ。
「パードレの宗旨、そのものの正邪をあげつろうておるのではない。エスパニヤの国、ポルトガル国、その他諸々の国には、パードレの宗旨はたしかに正とすべきであろうが、我々が切支丹を禁制にしたのは重々、勘考の結果、その教えが今の日本国には無益と思うたからである」…
「正というものは、我々の考えでは、普遍なのです」司祭は言った。「…もし正が普遍でないという気持ちがあれば、どうしてこの苦しみに多くの宣教師たちが耐えられたでしょう。正はいかなる国、いかなる時代にも通づるものだから正と申します。ポルトガルで正しい教えはまた、日本国にも正しいのでなければ正とは申せません」…
「パードレたちは悉く同じことを言う。だが・・・ある土地では稔る樹も、土地が変われば枯れることがある。切支丹とよぶ樹は異国においては、葉も茂り花も咲こうが、我が日本国では葉は萎え、つぼみ一つつけまい。土の違い、水の違いをパードレは考えたことはあるまい」(注4)
以下は、棄教した司祭フェレイラとロドリゴの会話である。
「…お前の眼の前にいるのは布教に敗北した老宣教師の姿だ」…「二十年間、私は布教してきた」…「知ったことはただこの国にはお前や私たちの宗教は所詮、根をおろさぬということだけだ」
「根をおろさぬのではありませぬ」司祭は首をふって大声で叫んだ。「根が切りとられたのです」
だがフェレイラは司祭の大声に顔さえあげず眼を伏せたきり、意志も感情もない人形のように、「この国は沼地だ。やがてお前にも分かるだろうな。この国は考えていたより、もっと怖ろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった」(注5)
遠藤の小説「沈黙」における沼地のイメージは、日本の文化的土壌にキリスト教を根付かせることの難しさを巧みに表現した比喩である。しかしキリスト教が日本に土着化できなかった責任の一端は、キリスト教自身にもあるとみなければならない。キリスト教はすべての文化を超越する普遍的な真理であると自負しながらも、実際には西洋の文化を神に祝福されたものとし、それ以外の文化や宗教については「罪深いもの」「次元の低いもの」として否定的な態度をとる場合が多かった。それだけに土着の価値を重んじる日本人にはどうしても違和感を与えざるをえなかったのだ。このことはキリスト教が日本文化を研究して、真に日本人の精神や文化になじむような表現方法を開発するのを怠ってきたということである。
(注1)参考は百科事典「ブリタニカ」年鑑2009年版(データは2008年現在)(注2)Calro Caldarola, Christianity: The Japanese Way. (Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1979), p.15. 「バタ臭い」とは、バターの匂いがする、すなわち西洋臭いという意味である。日本人の朝食はご飯と味噌汁であるのに対して、西洋人の朝食はパンにバターを塗ったものであるという違いから、昔の日本人は西洋的なものを「バタ臭い」と呼んで揶揄した。
(注3)Owen Chadwick, The Reformation. (New York: Penguin Books, 1964), pp.340-2. 「少なくとも表面上は絶滅」と言っているのは、潜伏切支丹や隠れ切支丹がいたからである。
(注4)遠藤周作『沈黙』新潮社文庫、1981年、p.140-1
(注5)同上、p.188-9